水村美苗さんの最新長篇小説『大使の妻』(上下巻)を読みました。
軽井沢の追分に建つ山荘を舞台に、元大使夫妻の謎めいた行方と、数奇な半生が描かれる壮大な物語です。
「なぜ夫妻は姿を消したのか?」というミステリーに惹かれて、気づけば上下巻を一気に読破。
そして読後に残ったのは、「日本人とは何か」という問いでした。
高原文学が好きな私にとって、この作品はただの小説ではなく、自分の生き方を映す鏡のように感じられたのです。
『大使の妻』とはどんな小説?
基本情報
・著者 水村美苗
東京生まれ。12歳で渡米。イェール大学仏文科卒業、同大学院博士課程を修了。いったん帰国ののち、プリンストン、ミシガン、スタンフォード大学で日本近代文学を教える。1990年『續明暗』で芸術選奨新人賞を、1995年『私小説 from left to right』で野間文芸新人賞を、2002年『本格小説』で読売文学賞を、2008年『日本語が亡びるとき――英語の世紀の中で』で小林秀雄賞を、2012年『母の遺産 新聞小説』で大佛次郎賞を受賞。
新潮社公式サイトから引用
・刊行 上巻 2024年9月26日
・舞台 軽井沢・追分の山荘を中心に、日本と世界を行き来する壮大な時間軸
あらすじ(ネタバレなし)
世界がパンデミックに覆われた2020年。
翻訳者ケヴィンは、軽井沢・追分の小さな山荘で、隣家を見やっていました。
そこはかつて元外交官夫妻の住まいでしたが、前年に二人は忽然と姿を消し、今は静まり返ったまま残されていたのです。
やがてケヴィンは、夫妻から聞いた貴子の数奇な人生を日本語で書き残す決意をします。
孤児から身を立てた謎の男、戦後昭和の軽井沢、そして四十年にわたる愛と恩讐。
失われた「日本」への思慕を抱えながら描かれる、大ロマン小説です。
この作品の魅力
ミステリー仕立てで一気に読める
「なぜ夫妻は軽井沢から姿を消したのか?」
その謎が物語全体を引っ張っていきます。
別荘というのは、静かに過ごしたい人にとっては隣人がとても重要です。
もしも隣で大人数が集まってBBQばかりしていたら、「外れを引いた」と感じてしまうでしょう。
だからこそ、静かな山荘に住む大使夫妻の存在や、彼らが忽然と姿を消したことには大きな意味があるように思えるのです。
文学作品でありながら、純粋に“先が気になる”小説としても楽しめ、私は夢中になってページをめくりました。
軽井沢・追分の空気感

軽井沢・追分と聞くだけで、独特の空気を思い浮かべる方も多いでしょう。
静かな森、澄んだ空気、歴史ある別荘地としての文化。
『大使の妻』には、その土地ならではの雰囲気が鮮やかに描かれています。
私自身、昨年八ヶ岳の友人の別荘に招かれ、都会とは全く異なる時間の流れを体験しました。
木立に囲まれた山荘にいると、心が研ぎ澄まされるような感覚があります。
読書中、そのときの記憶が重なり、まるで自分が追分で物語を見守っているかのように思えました。
夫人・貴子の存在感
物語の中心にいるのが、元大使夫人の貴子です。
能を舞い、着物を纏い、古風でありながらも凛としたその姿は、ただの登場人物ではなく「失われつつある日本」を象徴しているように感じました。
彼女には、高貴さと品格が漂っており、大使夫人という特別な立場そのものが持つステイタスに、読んでいて思わず憧れを抱かずにはいられませんでした。
その気品は、物語の空気を一段と格調高いものにしてくれます。
貴子の人生には、伝統的な日本人女性の姿と、個人として自由に生きようとする強さが共存しています。
彼女の歩みを追ううちに、「日本人とは何か」という問いが、物語の中から読者の心に自然と立ち上がってくるのです。
また、彼女の人間関係はきらびやかであると同時に、どこか切なく、時代そのものの移ろいを映していました。
華やかさと陰り、その両方を抱えながら生きる姿が強く印象に残ります。
ポストコロナ小説
『大使の妻』がユニークなのは、単なる歴史小説でも純文学でもなく、2020年というパンデミック下から物語が始まる点です。
マスクや自粛生活を経験した私たちにとって、その描写は記憶に生々しく残っており、読むだけで当時の空気感がよみがえってきます。
閉ざされた山荘での生活や、世界が突然分断される状況は、まさに私たち自身が体験した日常そのものでした。
そこに昭和の軽井沢の回想が重なり、「かつての日本」と「今の日本」とが交錯する構成になっているのが非常に印象的です。
この小説は過去を描くだけでなく、ポストコロナの時代に生きる私たちに、「日本人とは」「日本とは」と問いかけてきます。
過去と現在をつなぎながら読むことで、作品は一層奥行きを増して感じられました。
私の感想

『大使の妻』は、私の大好きな山の家が舞台になっているだけでなく、外国からの目線で見る日本についても詳しく書かれている点が、大いに興味を引きました。
更に、夫妻なぜ軽井沢から姿を消したのか?という謎が物語を引っ張り、上下巻を通して夢中になって読み進めることができました。
別荘に暮らす人にとって、隣人がどのような人物かはとても重要です。
静かに過ごしたいと願っていても、もし隣で大人数が集まって騒いでいたら「外れた」と感じてしまうでしょう。
だからこそ、静かな山荘に暮らしていた大使夫妻の存在、そして彼らが忽然と姿を消したという事実には、特別な重みがあるように感じられました。
また、軽井沢・追分の描写は、昨年私が八ヶ岳の友人の別荘に招かれた体験と重なりました。
木立に囲まれた山荘で過ごすと、都会とはまったく違う時間の流れがあり、心が研ぎ澄まされていくような感覚があります。
生活の拠点が山にもあるということが、私にはとても羨ましく思えました。
日常を都会で過ごしながらも、夏や週末には静かな山荘に身を置く。
2つの生活の場で、自分自身がどんなことを考え、感じるのか。
きっと違うのではないかと想像しています。
そしてなんといってもこの小説の魅力はキャラクターがミステリアスで魅力的なところ。
一番の謎は夫人・貴子です。
大使夫人という特別な立場から放たれる高貴な雰囲気に、ただの憧れを超えて「日本人としての誇りや美意識」を考えさせられたのです。
読み進めるうちに、「日本人とは何か」という大きなテーマが、自然に自分の中でも立ち上がってきました。
でも、この小説の本当に興味深いのは、実は夫人は・・・ということです。(ここは秘密にしておきます)
日本国大使とか、山の家、日本文化のほかに、読者は過去の歴史的な出来事の詳細を知ることになります。
それらが物語に重なり合うことで、深くその感覚に浸れる作品でした。
私の頭の中に登場人物のビジュアルまで生まれてしまったほどです。
『大使の妻』はこんな人におすすめ
『大使の妻』は、純文学としての深みと、ミステリー仕立ての面白さを併せ持つ作品です。
読んでいて感じたのは、次のような方に特におすすめできるということです。
- 山の家や別荘といった舞台に惹かれる人
静かな環境で流れる時間や、自然の中での人間模様に興味がある方にはぴったりです。 - 「日本人とは何か」という問いに関心がある人
外国人の目線を通して描かれる日本の姿や、貴子の生き方は、読む人に考えを促してくれます。 - 本格的な文学作品を読みたいけれど、物語性も重視したい人
上下巻にわたる壮大なスケールでありながら、謎解きのような要素があり、最後まで夢中で読めます。 - 戦後から現代へと続く歴史や文化を背景にした物語を楽しみたい人
過去の出来事が物語に絡み合うことで、日本の近代史を小説を通して追体験することができます。
まとめ
水村美苗の『大使の妻』は、軽井沢の山荘を舞台に、日本と世界、過去と現在が交錯する壮大な小説でした。
隣人の存在や山荘での時間の流れ、そして夫人・貴子の高貴な雰囲気を通して、「日本人とは何か」というテーマが深く心に響きました。
ミステリーとしても純文学としても楽しめる一冊であり、読後には森の静けさとともに、自分自身の生き方を考えさせられる余韻が残ります。
50代の私たちの世代はかなり楽しめると思います。
残念ながら現時点では文庫はありません。
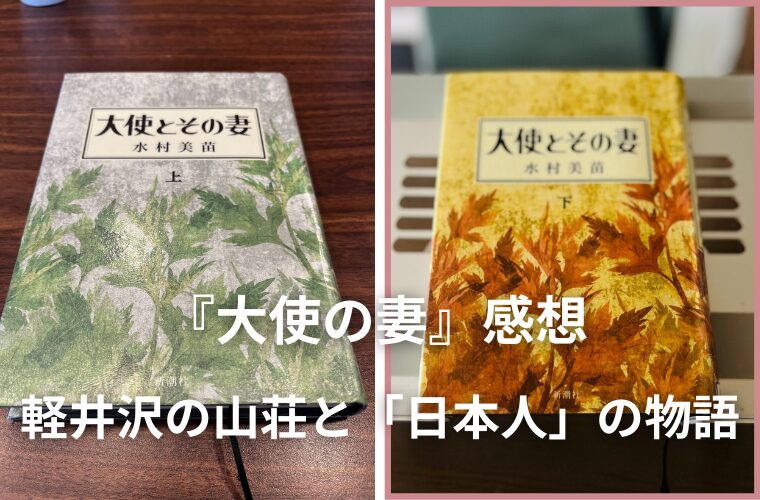


コメント